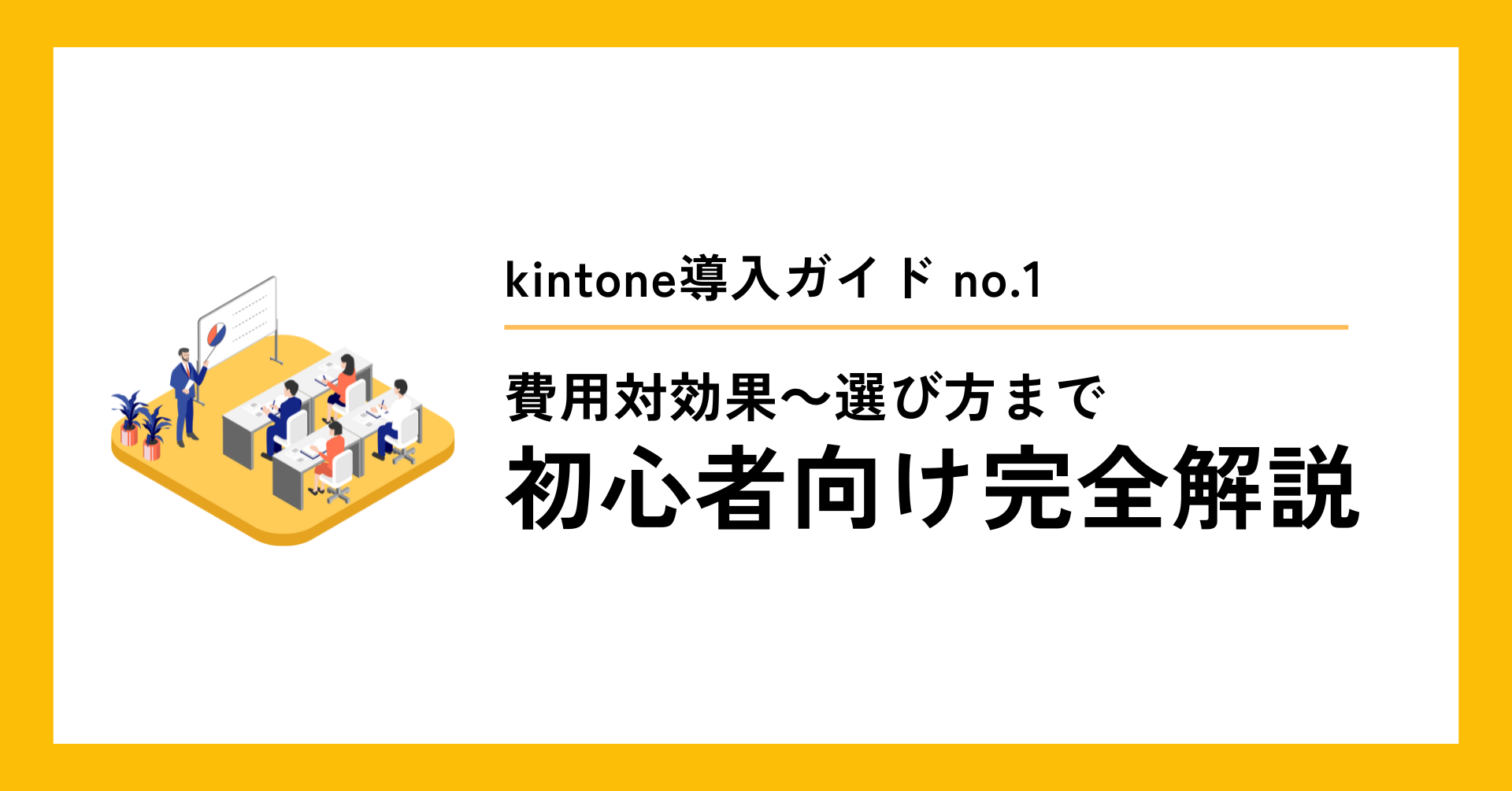
近年、企業のデジタル化が急速に進む中、業務効率化のためのツール導入は避けて通れない課題となっています。特に中小企業においては、限られたリソースで最大の効果を得るための選択が重要です。そんな中、注目を集めているのが「kintone(キントーン)」です。
kintoneは、サイボウズ社が提供するクラウド型の業務アプリ開発プラットフォームで、プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの操作で簡単に業務アプリを作成できるのが特徴です。しかし、「導入すべきか」「どのように活用すれば効果的か」と悩む経営者や情報システム担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、kintone導入を検討している方々に向けて、メリットから選定ポイント、費用対効果の考え方まで、初心者にもわかりやすく解説します。
目次
kintoneとは?基本機能と主な特徴

kintoneは、日本の企業向けグループウェアで知られるサイボウズ社が提供するクラウドサービスです。2011年11月7日に提供開始以来、大企業から中小企業まで幅広い規模の企業で導入され、2024年時点では30,000社を超える導入実績があります。
■ 基本的な機能
kintoneの基本となるのは、「業務アプリ」と呼ばれるデータベースです。この業務アプリを使って、以下のようなさまざまな業務を管理できます。
●顧客管理: 顧客情報の一元管理、対応履歴の記録
●案件管理: 営業案件の進捗状況、受注確率の管理
●プロジェクト管理: タスク割り当て、進捗状況の可視化
●備品管理: 社内備品の在庫・貸出状況の管理
●申請業務: 稟議書、経費精算、休暇申請などの電子化
アプリ作成にはプログラミングの知識は必要なく、必要な項目をドラッグ&ドロップで配置するだけで作成できます。また、テンプレートとして提供されているアプリを使えば、さらに簡単にスタートできます。
■ kintoneの主な特徴
1.簡単なアプリ作成: プログラミング不要で業務に合わせたアプリを作成可能
2.カスタマイズ性: 業務に合わせた細かい設定が可能
3.コミュニケーション機能: 各レコード(データ)に対してコメントを残せる
4.通知機能: 更新や期限などを自動で通知
5.アクセス権限管理: 部署やチームごとに閲覧・編集権限を設定可能
6.モバイル対応: スマートフォンやタブレットからもアクセス可能
7.API連携: 他のシステムとの連携が可能
8.プラグイン拡張: 機能を拡張するプラグインが多数用意されている
特にコミュニケーション機能が組み込まれている点は、単なるデータベースとは一線を画します。データの共有だけでなく、そのデータに関する議論や判断もkintone上で完結できるため、メールやチャットとの行き来が減り、業務効率が向上します。
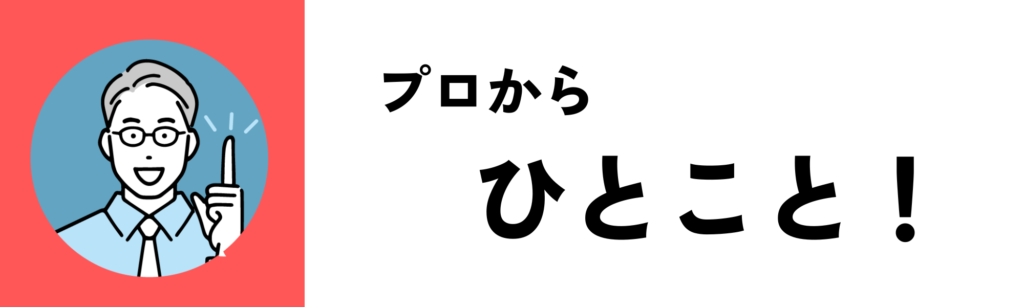
kintoneを理解するなら、「レゴブロック」をイメージするとわかりやすいでしょう。レゴブロックは子どもでも簡単に組み立てられますが、組み合わせ方次第で複雑な建造物も作れます。kintoneも同じで、シンプルな操作で始められますが、工夫次第で複雑な業務プロセスも再現できるのです。
たとえば、レゴの基本セットだけでは満足できない上級者が拡張パーツを追加するように、kintoneも基本機能だけでは足りなくなったら、プラグインやAPIで機能を拡張できます。「最初は簡単に、成長に合わせて進化させられる」という点が、kintoneの最大の魅力なのです。
kintone導入のメリットと費用対効果

kintoneを導入することで、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。また、投資に見合った効果を得るためには、どのように考えればよいのでしょうか。
■ 主なメリット
1.業務の可視化と標準化
多くの企業では、業務プロセスや情報が「属人化」していることが課題です。kintoneを使えば、これまで個人のノウハウや経験に依存していた業務を「見える化」し、標準化できます。たとえば、A社では営業担当者ごとに顧客情報の管理方法がバラバラでしたが、kintone導入後は統一された形式で管理できるようになり、担当者が不在でも必要な情報にアクセスできるようになりました。
2.情報共有の円滑化
kintoneは単なるデータベースではなく、コミュニケーション機能が組み込まれています。データに直接コメントを付けられるため、そのデータに関する会話が一元化され、メールやチャットツールを行き来する必要がありません。製造業のB社では、生産計画の変更をkintone上で共有し、関連部署とのやり取りもすべてそこで完結させることで、コミュニケーションミスによる生産ロスが30%減少しました。
3.業務効率の向上
手作業や紙ベースの作業をkintoneで電子化することで、大幅な時間短縮が可能です。サービス業のC社では、紙の申請書で行っていた日報処理をkintoneに移行したところ、月あたり約40時間の工数削減に成功しました。さらに、定型業務の自動化や承認フローの電子化により、意思決定のスピードも向上します。
4.データの活用促進
散在していたデータをkintoneに集約することで、データ分析が容易になります。卸売業のD社では、各営業担当者が個別に管理していた顧客データをkintoneに統合し、購買傾向の分析が可能になったことで、クロスセルの機会を特定し、売上が15%向上しました。
■ 費用対効果の考え方
kintone導入の費用対効果を検討する際は、以下の観点で考えると良いでしょう。
1. 直接的なコスト削減効果
・紙や印刷にかかるコスト削減
・重複作業の排除による工数削減
・オフィススペースの有効活用(書類保管スペースの削減)
例えば、50人規模の企業で月間500件の申請書処理をkintoneに移行した場合、紙代・印刷代で年間約10万円、処理工数で年間約200時間の削減が見込めます。時給換算すれば年間400万円以上の効果になります。
2. 間接的な効果(定量化しにくいが重要な効果)
・意思決定の迅速化による機会損失の防止
・ミスや手戻りの減少によるクオリティ向上
・情報共有の質向上によるイノベーション創出
・従業員満足度の向上と優秀な人材の確保
これらの効果は数値化が難しいものの、中長期的な企業成長に大きく寄与します。実際、kintoneを活用して社内コミュニケーションを活性化させた企業では、離職率が低下し、新規事業のアイデア創出も増加したという事例もあります。
3. ROI(投資対効果)の計算例
中小企業の場合、kintone導入の初期費用と年間ランニングコストの合計は、おおよそ以下のようになります(2024年時点)。
●初期費用: 導入支援・設定費用として50〜100万円
●年間ライセンス料:
ライトコース: 月額1,000円/ユーザー(10ユーザーで年間12万円)
スタンダードコース: 月額1,800円/ユーザー(10ユーザーで年間21.6万円)
ワイドコース: 月額3,000円/ユーザー(10ユーザーで年間36万円)
●保守・運用費用: 年間約30万円
これに対して、前述の直接的効果(年間400万円以上)だけでも十分にペイするケースが多く、さらに間接的効果を加味すれば、導入初年度からプラスのROIを実現できる可能性が高いです。
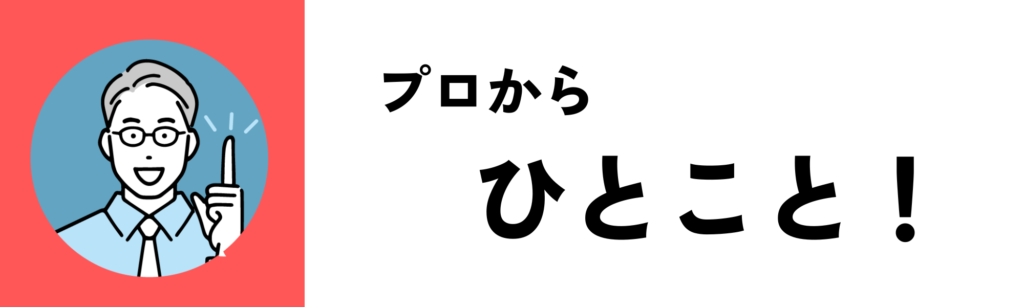
kintoneの費用対効果を考えるときは、「牛丼チェーン店のキッチン改革」を想像するとわかりやすいですよ。
かつての牛丼店は、注文を聞いて、肉を盛り、丼に盛り付け…というように、すべての工程を手作業で行っていました。それが今では、ボタン一つで注文情報が厨房に伝わり、自動湯沸かし器でお茶が出て、食券機で会計が済むようになりました。
kintoneも同じです。バラバラだった情報や手作業の流れを「システム化」することで、無駄な動きがなくなり、ミスも減り、店舗全体(会社全体)の回転率が上がります。初期投資は必要ですが、長い目で見れば「あのときシステム化して本当に良かった」と感じるでしょう。
ROIだけでなく「従業員がイライラせずに働ける」「お客様をお待たせしない」というような定性的な価値も大きいのです。数字には表れにくいこの価値こそ、長期的な企業の競争力になります。
kintone導入前に確認すべき3つのポイント

kintoneを導入する前に、自社の状況や目的に合致しているかを確認することが重要です。成功する導入のためには、以下の3つのポイントを事前に検討しましょう。
■ 1. 解決すべき業務課題の明確化
kintoneを導入する前に、「どのような課題を解決したいのか」を明確にしましょう。漠然と「業務効率化のため」と考えるのではなく、具体的な課題を洗い出すことが重要です。
良い例:
●営業担当者ごとに顧客情報の管理方法がバラバラで、情報共有ができていない
●紙の申請書による承認プロセスが遅く、決裁までに平均5日かかっている
●プロジェクトの進捗状況がリアルタイムで把握できず、問題の早期発見ができない
悪い例:
●なんとなく効率が悪そうだから
●他社も導入しているから
●ITツールを導入すれば何かが変わるだろう
具体的な課題を特定することで、どのようなアプリを作るべきか、どのような運用ルールが必要かが明確になります。当社で支援したE社では、導入前に「営業活動の見える化」「見積書作成時間の短縮」「顧客フォローの漏れ防止」という3つの課題を特定し、それぞれに対応するアプリを段階的に構築したことで、スムーズな導入と高い効果を実現しました。
■ 2. 社内の推進体制と運用ルール
kintoneは比較的簡単に導入・設定できるツールですが、効果的に活用するためには適切な推進体制と運用ルールが欠かせません。
推進体制で考慮すべき点:
●経営層のコミットメント(トップダウンの推進力)
●現場のキーパーソン(ボトムアップの実行力)
●IT部門や外部パートナーのサポート体制
特に重要なのは「kintone管理者」の存在です。この役割を担う人が、アプリの作成・改善や社内からの要望対応を行います。社内にIT知識を持つ人材がいない場合は、外部パートナーとの連携も検討しましょう。
運用ルールで考慮すべき点:
●データ入力のタイミングと責任者
●情報の更新頻度
●アクセス権限の設定方針
●バックアップと情報セキュリティ
F社の事例では、導入当初は利用が進まなかったものの、「朝会でkintoneの案件情報を見ながら進捗確認を行う」というルールを設けたことで、データ入力が習慣化し、3ヶ月後には全社で活用されるようになりました。
■ 3. 段階的な導入・拡張計画
kintoneは多機能なツールですが、一度にすべての機能を導入しようとすると失敗するリスクが高まります。成功のポイントは「小さく始めて、段階的に拡張する」という考え方です。
段階的導入の例:
1.フェーズ1(1〜2ヶ月目): 最も課題感の強い1つの業務で小規模に始める(例: 営業案件管理)
2.フェーズ2(3〜4ヶ月目): 関連する業務へ拡張(例: 顧客管理、商談記録)
3.フェーズ3(5〜6ヶ月目): 部門を跨いだ連携(例: 営業〜製造〜物流の連携)
4.フェーズ4(7ヶ月目〜): 高度な活用(API連携、自動化、分析活用)
小売業のG社では、最初に店舗の日報アプリから始め、成功体験を積んだ後に在庫管理、発注管理へと拡張しました。全社一斉ではなく成功事例を作りながら広げていくことで、現場の抵抗感も少なく、スムーズな導入が実現しました。
また、将来的な拡張性も考慮しておくことが重要です。例えば、最初はシンプルな顧客管理から始めても、将来的にはMAツールとの連携や分析機能の活用などを視野に入れた設計にしておくと、後々の拡張がスムーズになります。
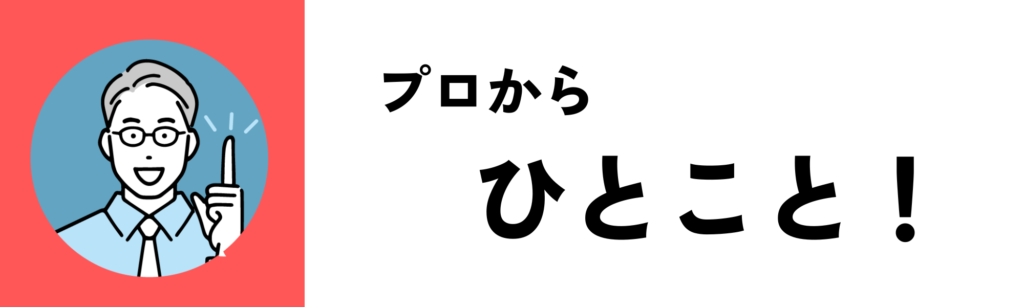
kintone導入は、「新しい家に引っ越す」ようなものです。引っ越しの前には「なぜ引っ越すのか」(課題)を明確にし、「誰が何を運ぶのか」(推進体制)を決め、「段階的に荷物を運び入れる計画」(段階的導入)を立てますよね。
いきなり全ての家具を運び込もうとすると、配置に困ったり、通路が塞がれたりします。同様に、kintoneもいきなり全ての業務を移行しようとすると混乱が生じます。まずはリビングの家具(最重要業務)だけを配置し、使い心地を確かめながら、徐々に他の部屋の家具も運び入れていくのが理想的です。
また、家の間取り(kintoneの設計)も重要です。将来、子どもが増えたり(業務拡大)、在宅勤務スペースが必要になったり(新しいワークスタイル)することを見越した間取りにしておくと、後々の改修の手間が省けます。kintoneも同様に、将来の拡張性を考慮した設計が大切なのです。
kintone導入・活用の具体的な進め方
kintoneの導入を決めたら、次は具体的にどのように進めればよいのでしょうか。ここでは、導入から活用までのステップを解説します。
■ Step 1: 導入準備と環境設定
まずは、kintoneの利用環境を整え、基本的な設定を行います。
主な作業項目:
1.契約とライセンス: ユーザー数の見積もりと契約手続き
2.管理者の選任: 社内のkintone管理者を決定する
3.基本設定: スペース構成、アクセス権限のポリシー決定
4.セキュリティ設定: パスワードポリシー、IP制限などの設定
5.ユーザー登録: 利用者のアカウント作成と初期設定
この段階での注意点は、将来的な拡張を見据えた設計です。例えば、部署やプロジェクトごとに「スペース」を作成し、その中にアプリを配置する構成にしておくと、後々の管理が容易になります。
物流会社のH社では、導入初期に「営業スペース」「運行管理スペース」「経理スペース」「全社共有スペース」という4つのスペースを設け、アクセス権限を整理したことで、情報漏洩リスクを最小化しながらも必要な情報共有が実現できました。
■ Step 2: モデルアプリの構築と運用テスト
環境が整ったら、最初のモデルアプリを構築し、小規模で運用テストを行います。
主な作業項目:
1.対象業務の選定: 成功確率が高く、効果が見えやすい業務を選ぶ
2.要件定義: 必要な項目、ワークフロー、アクセス権などの洗い出し
3.アプリ設計: フォームレイアウト、プロセス設定、通知設定など
4.プロトタイプ作成: まずは簡易版を作成して機能確認
5.テスト運用: 限定メンバーでの試験運用と改善
モデルアプリ選定のポイントは、「業務頻度が高く」「関係者が少なく」「効果が可視化しやすい」業務を選ぶことです。例えば、日報管理や備品管理などは比較的シンプルで効果も見えやすいため、最初のアプリとして適しています。
飲食チェーンのI社では、最初に「店舗点検アプリ」を構築しました。週1回の店舗点検業務をkintoneに移行することで、点検漏れの防止と報告書作成の手間削減という明確な効果が得られ、現場からの信頼獲得につながりました。
■ Step 3: 全社展開と定着化
モデルアプリの成功を受けて、対象業務や利用者を拡大していきます。
主な作業項目:
1.成功事例の共有: モデルアプリの効果を社内に発信
2.利用者教育: 操作方法や運用ルールの研修実施
3.サポート体制の確立: 質問や要望に対応する窓口の設置
4.追加アプリの開発: 段階的に対象業務を拡大
5.利用状況のモニタリング: 活用度の確認と促進策の実施
この段階で重要なのは「成功体験の共有」と「小さな成功の積み重ね」です。一度に多くのアプリを展開するのではなく、1つずつ成功事例を作り、その効果を共有しながら広げていくことで、自然な定着が促進されます。
コンサルティング会社のJ社では、最初の3ヶ月は月1回の「kintone活用報告会」を開催し、各部署のkintone活用事例と効果を共有しました。これにより部署間の良い競争が生まれ、自発的なアプリ開発が促進されました。
■ Step 4: 発展的活用と継続的改善
基本的な活用が定着したら、より高度な活用方法にチャレンジし、継続的な改善を行います。
主な作業項目:
1.アドバンスド機能の活用: グラフ集計、カスタマイズ機能の活用
2.外部システム連携: APIを使った他システムとの連携
3.業務プロセスの最適化: kintoneを前提とした業務フローの再設計
4.データ分析の高度化: 蓄積されたデータの分析と活用
5.改善サイクルの確立: 定期的な振り返りと改善の仕組み化
例えば、製造業のK社では、基本的な生産管理アプリが定着した後、APIを活用して基幹システムとの連携を実現しました。受注データが自動で生産管理アプリに反映され、生産完了情報が基幹システムに自動連携されることで、二重入力がなくなり、さらなる業務効率化を実現しています。
また、定期的な「kintone改善会議」を設け、利用者からのフィードバックを集め、継続的に機能や運用ルールを改善していくことも重要です。システムは「作って終わり」ではなく、継続的に進化させていくものだという認識が大切です。
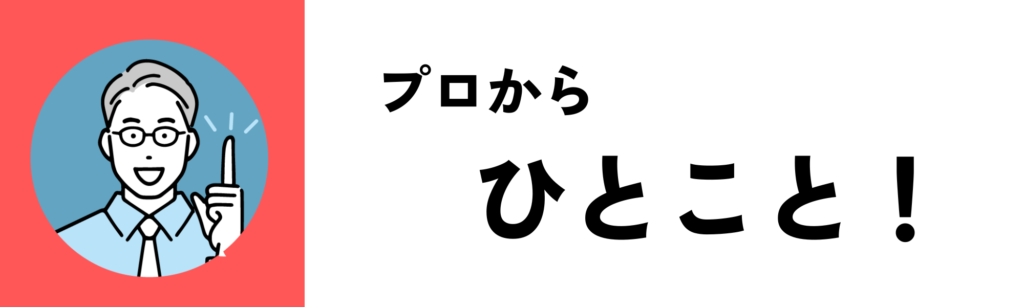
kintoneの導入プロセスは、「料理教室を開くようなもの」だと考えるとわかりやすいでしょう。
最初は調理器具を揃え、教室のレイアウトを決める(環境設定)ところから始まります。次に、比較的簡単で失敗しにくい「基本のオムライス」のような一品(モデルアプリ)から教えます。生徒が基本を理解したら、少しずつレシピを増やし(追加アプリ)、料理会(活用報告会)で成果を披露し合います。
そして腕が上がってきたら、高級な調理器具(アドバンスド機能)を導入したり、フュージョン料理(外部連携)にチャレンジしたり。定期的に「今月のベストレシピ」を選んで改良していく(継続的改善)ことで、料理教室全体のレベルが向上していきます。
大切なのは、いきなりフランス料理のフルコースに挑戦しないこと。小さな成功体験を積み重ね、「料理って楽しい!」という気持ちを育てることが、長続きする料理教室(=定着するkintone活用)の秘訣なのです。
まとめ:kintone導入の成功に向けて

ここまで、kintoneの基本機能から導入メリット、導入前の確認ポイント、そして具体的な進め方まで解説してきました。最後に、kintone導入を成功させるためのポイントをまとめます。
■ 成功のための5つのポイント
1.明確な目的設定
「なぜkintoneを導入するのか」という目的を明確にし、解決したい具体的な課題を特定しましょう。漠然とした理由での導入は効果が見えにくく、定着しない原因となります。
2.トップダウンとボトムアップの両立
経営層の理解とサポート(トップダウン)と、現場の主体的な参加(ボトムアップ)の両方が重要です。特に現場のキーパーソンを巻き込み、「自分たちのシステム」という意識を育てましょう。
3.小さく始めて段階的に拡大
一度にすべての業務をkintoneに移行しようとせず、まずは小規模なモデルケースから始め、成功体験を積み重ねながら段階的に拡大していきましょう。
4.継続的な改善サイクル
kintoneは「導入して終わり」ではなく、利用者の声を反映しながら継続的に改善していくことが重要です。定期的な振り返りと改善の仕組みを作りましょう。
5.専門家との連携
社内にIT知識や業務設計のノウハウがない場合は、外部の専門家と連携することも検討しましょう。初期設計や導入支援、運用定着までサポートを受けることで、成功確率が高まります。
■ 最後に
kintoneは非常に柔軟性の高いツールであり、使い方次第で多様な価値を生み出します。「とりあえず導入してみる」のではなく、本記事で解説したポイントを押さえた計画的な導入を心がけることで、業務効率化だけでなく、組織文化の変革や競争力の強化にもつながるでしょう。
デジタル化の波が加速する今、中小企業こそkintoneのようなツールを活用して、限られたリソースを最大限に活かす経営が求められています。kintone導入を通じて、貴社のビジネスが一層発展することを願っています。
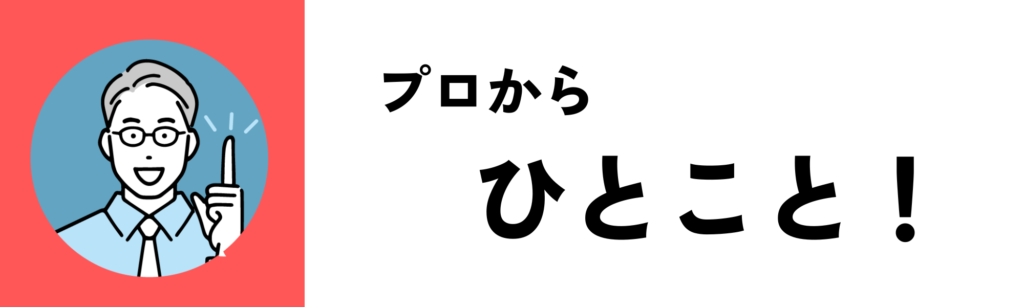
kintone導入は、「新しい楽器を手に入れる」ようなものです。立派なピアノを買っても、弾き方を学ばなければ美しい音色は奏でられません。また、いきなり難曲に挑戦するのではなく、簡単な曲から始めて徐々にレベルアップしていくのが上達の秘訣です。
そして何より大切なのは「楽しむ心」です。チームで一緒に音楽を奏でる(kintoneを活用する)喜びを共有できれば、自然と練習(活用)も続き、やがては素晴らしいオーケストラ(効率的な組織)が完成します。
デジタル化やシステム導入は手段であって目的ではありません。最終的には「より良い仕事」「より良い組織」を目指すためのものです。kintoneというピアノで、貴社ならではの素敵な音楽を奏でてください。私たちはその演奏を全力でサポートします。
